肉球について教えて!
肉球について教えて!
私たち人間にはない肉球。動物たちの肉球、ついつい触りたくなるのは私だけではないと思います。あのブニブニ感がなんともたまらないですよね。そして色々調べていると、肉球を模ったグッズや肉球の写真を集めた本などといった肉球に関わるものがたくさんありました。それほどみんなあのブニブニ感に魅了されているのかもしれません。
肉球はどんな動物にあるの?
まず肉球とは、食肉目の動物の足裏部に見られる、もりあがった無毛の部分のこと。とありました。しかし食肉目の動物のなかにも例外がいて肉球のついていないものもいるようです。
食肉目といわれてもどんな動物がいるのかピンとこないと思いますので図で説明します。 これをみればどんな動物がいるのかだいたいわかると思います。
肉球の働きは?
肉球はとても厚い表皮と柔らかい脂肪の組織で出来ています。この厚い表皮は靴底の役目、柔らかい脂肪の組織はクッションの役目を持っています。獲物に接近する際に気づかれないように足音を消したり、歩行時や樹上などから飛び降りるときの衝撃を緩和します。表皮の厚さはワンちゃんよりネコちゃんのほうが薄いようです。また、以前熱中症のお話をした時にも言いましたが、動物たちは肉球から汗を出しています。
肉球の間の毛は長毛種では長く、短毛種では短い傾向があります。長い毛は雪や氷で滑らないようにし、冷たさから肉球を守るためのものです。暑いところで生活する場合は地面の熱さから肉球を守り、砂で滑らないようにするといった役目をもっています。
しかし、家の中で暮らしている場合、長い毛があるためにフローリングや家具の上などですべってしまう危険性があります。そのような動物の肉球の間の毛は短く刈ってあげるといいでしょう。

ワンちゃんとネコちゃんの肉球の違い


ワンちゃんの肉球はネコちゃんと比べて表面に小さな突起の集まりで出来ています。このため、触り比べてみるとネコちゃんの方がなめらかに感じられると思います。この違いはワンちゃんがこの突起をスパイクのように使い大地を走り回ったり、ネコちゃんは忍者のようにヒタヒタと静かに歩くという特徴を活かすことができます。
またネコちゃんの肉球の表皮はワンちゃんに比べて薄いため、触感も発達していてネコちゃんは前足で顔を洗ったり、獲物やおもちゃを手でつかんだりすることができます。
動物にとって、足の裏を触られるのをとても嫌がる場合が多いです。爪きりや足の裏の毛のカットなど日ごろからコミュニケーションをはかっていただき、肉球も観察してあげてください。
外耳炎ってどういう病気?
外耳炎ってどういう病気?
最近、朝晩は涼しく感じられるようになってきましたがまだまだ名古屋は日中暑いです。暑い時期に多い病気の一つとして、外耳炎という病気があります。皆さんも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか?
耳の構造
「外耳」とは、集音器ともいえる耳介から外耳道、鼓膜までの部位をいいます。 犬や猫の外耳は中間部分でL字型に折れ曲がっているため人に比べ外耳炎が起きやすい構造になっています。また犬はアポクリン腺という脂質を分泌する腺が発達しているので人に比べて耳垢が多くなります。
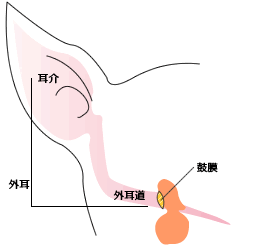
主な原因
耳ヒゼンダニ
耳ヒゼンダニとは、通常耳の中(外耳)にだけ寄生する、長さ0.2~0.3ミリほどのダニの一種です。普通は、子犬の時に母犬から感染することが多くみられますが、時には耳ヒゼンダニに感染した犬に接触して感染することもあります。体毛に付着した幼ダニや成ダニが耳の中に到達して定住して耳垢などを食べて繁殖します。成ダニは卵をどんどん産み、その卵から孵化した幼ダニが成長してさらに繁殖します。かゆみがあり、耳垢は黒色や茶褐色のものが多いです。
マラセチア
マラセチアとは、酵母菌の一種であり真菌(カビ)の仲間です。このマラセチアは正常な犬や猫の耳道内にも存在していて普段は病原性を示しません。ところが、何らかの原因で犬の免疫力、抵抗力が低下したり、すでに外耳炎の兆候があったり、脂っぽくベタベタした耳垢がたまりやすいといったような環境が整っていたりすれば、マラセチアなどが外耳で繁殖することになります。またアレルギー疾患などと関連して二次的に発生しやすく再発や慢性化することがあります。耳垢は茶褐色のものが多く、独特なにおいがあります。
細菌
マラセチアと同様に正常な耳道内にも存在していますが、何かの影響で繁殖し症状を示します。 耳垢は繁殖している細菌の種類にもよりますが黄色や緑黄色ものが多く、痛みを示すこともあります。
ではさっそくワンちゃん、ネコちゃんの耳の中をチェックしてみましょう。

どうでしたか?心配なようだったらぜひ一度動物病院に行ってチェックしてもらってください。また、耳は日ごろのケアも大切になります。間違ったケアをしていると外耳炎を悪化させてしまうこともありますのでぜひケアの仕方も一度見直してみてください。
最後にちょっと、人・犬・猫の聴力を調べてみました。資料により若干違いがありますが低音に関してあまり差はないようですが、高音は人では2万ヘルツ、犬では4万ヘルツ、猫では6万ヘルツ以上の音を聞く能力があるそうです。 ネコちゃんってすごいですね。
ペット保険って何?
ペット保険って何?
当院でも初めて来院された患者さんには、‘ペット保険に入られていますか?’とお尋ねします。ほとんどの方が‘入っていません’という答えです。中には‘ペット保険って何?’と聞かれる方もいらっしゃいます。ペットを飼っている方でもまだまだ保険について浸透していないというのが現状ではないでしょうか?
そこで今回はペット保険についてまとめてみることにしました。
ペット保険は30年ほど前にイギリスで始まったといわれています。日本の歴史はまだ浅く、現在取り扱い事業者は20社前後しかなく、そのほとんどが数年の実績しかありません。
海外では保険会社などによる販売が一般的ですが、日本では任意の共済事業者による無認可商品がほとんどです。2006年4月から法改正により無認可共済事業者も規制対象になりました。
加入できるペットは?
犬と猫が基本で、鳥やウサギ、フェレット、爬虫類などの入れるものもあります。ほとんどが加入年齢制限を設けていますが、一度入れば終身継続できます。
加入審査は?
原則的に自己申告による申告書の提出だけです。申告書には飼育状況や健康状態、過去の受診歴、予防接種の日付などを記入します。生年月日は推定でも問題ないようですが、うそを書くと給付金が支払われないこともあります。
保障の形式は?
○定率保障型(治療費の一定割合を給付)
○定額保障型(治療費に関係なく一定の金額を給付)
○実額保障型(限度額内で費用の全額を給付) の3種類です。
掛け金の形態は?
固定制と変動性に大別され、月払いで二千円前後から四千円前後が目安です。 変動制の場合、年齢や体重、種類によって金額が変わり、1年ごとに見直しがあるのが普通です。
保障される内容は?
通院や入院、手術、がんなどによる治療費の保障が中心となります。死亡保障やペットが他人に咬みついてけがを負わせた場合などの賠償保障、予防接種費用保障などが付帯したものもあります。
最近は動物医療も進歩し、動物たちも高齢化してきました。その一方で高齢ゆえに、心臓病やガンなど重い病気にかかり治療が長期で高額になるリスクも多くなりました。しかし、私たち人間と異なり、ペットには医療保険制度がなく飼い主さんの全額自己負担となります。ですから私たち獣医師は治療方針を決めるとき飼い主さんと相談し、例えば‘血液検査にはいくらかかり、レントゲン検査にはいくらかかります’というような値段の説明も行います。そういう話し合いを行い、治療費が払えないので今日は薬だけ下さいというような方も少なくありません。私たちは動物たちに対して一番いい治療を行いたいと思っていてもお金の問題で断念しなければいけない時が一番つらいです。そういう時、ふとこの子が保険に入っていればなあと思うことがあります。
治療費を考えることなく早い段階で検査を行い、治療の選択肢が拡大すれば結果として動物の苦痛の軽減、治療費の軽減につながると思います。決して保険を勧めているわけではありません。保険に入らず毎月、○ちゃん積み立てという形で貯金をされている方もいらっしゃいます。
私たち人間も動物も生き物である以上寿命があります。何の病気もなく寿命が迎えられるのが一番いいことだとは思いますし、私も願っています。でも病気はいつやってくるかわかりません。ですから飼い主さんもその心構えをしておいて欲しいのです。 そして私たち獣医師もできる限り、最高の治療、最低の料金で動物たちを治療できるよう努力していきたいと思います。
熱中症ってどういう病気?
熱中症ってどういう病気?
名古屋に住み始めて 1 年が経ちました。名古屋の夏は暑い!!といろいろな方から聞きますが、本当に‘暑い’ですね。最近も天気がいい日は夏を思わせるような陽気です。 愛犬 CERO くんの散歩も最近はお昼休みの時間に行くことが出来なくなりました。
全身を毛で覆われているワンちゃんにとっては、私たち人間以上に過ごしづらい季節がやってきます。人間は全身にある汗腺から汗をかくことで体温を調節できますが、ワンちゃん(ブタさんも)の汗腺は未発達で体温を調節する機能はほとんど備わっていません。暑い時や運動をした後などには、ワンちゃんは口を開けてあえぐことで熱を蒸散させています。そのため、湿度や気温が高く、換気の状況が悪い時等は十分に体温を下げることができません。熱中症とは、 こうして体が調節できる範囲の温度を越えて体温が上昇するために多くの臓器が障害を受ける状態のことです。

熱中症になりやすい犬種
短頭種犬(シーズーやペキニーズ、パグ、ブルドッグ、ボクサーなど)
短頭種のワンちゃんたちは、解剖学的に首の部分が圧迫されていて、のど(喉頭)が狭く、体温放散の主役である呼吸の機能に問題が多い犬種です。また、上あごの奥の部分(軟口蓋)が気管の入り口に近接しているため、息を吸うたびに気管内に吸引されて気道をふさぎ、呼吸がしづらくなります。
肥満の犬
肥満、肥満傾向のワンちゃんは首の部分にも脂肪がたっぷりとついて、さらに気管を圧迫しのどを通る空気量が少なくなります。
子犬・老犬
子犬は、まだ体温を調節する機能がきちんと働きません。また子犬は成犬よりも体温が高いので、体温がすぐに 40 ℃を超えてしまいます。
老犬は、体温を調節する機能が衰えてきています。持病がある場合は特に注意が必要です。熱中症は脳にも内臓にも大きな負担がかかります。 子犬や老犬は健康な成犬が熱中症になるよりも、後遺症が残る危険性、死亡する危険性ははるかに高いことを心に留めておいてください。 その他にも、北方生まれの犬種(ハスキーやボルゾイなど)、被毛が厚い犬種(シェルティー、ピレネーなど)、毛色が黒い犬も熱中症になりやすいと言えます。
症状
初期症状はパンティング(あえぎ呼吸)と呼ばれる激しい開口呼吸と、それに伴う大量のよだれです。暑さで元気がなく、ハァハァとあえいでいれば熱中症の疑いがあります。また目が充血したり、口の粘膜が白っぽくなるのもよく見られる症状です。
ぐったりしたまま、呼吸が浅くなる、熱がある等の症状をそのまま放置すると、下痢・嘔吐、痙攣発作、血圧低下、呼吸不全になります。重傷になると短時間で死に至ることもあります。
家庭での応急処置
発見が早く、まだ意識があれば、冷たい水をたくさん飲ませ、またお風呂場などで体に直接水をかけるなど冷やして体温を下げてあげることが大切です。急なときに思いつかない方が多くいますので、ぜひ覚えておいてください。
また熱中症がひどく、意識不明の場合は水を飲ませることができないため、点滴などの緊急処置が必要になります。まずお風呂場などで水をかけ急いで体温を下げる努力を行い、動物病院に連絡してください。 熱中症は命にかかわる恐ろしい病気です。しかし、飼い主さんが少し気をつけるだけで防げる病気でもあります。真夏の締め切った部屋の中に留守番をさせたり、少しだけと車の中に置いて出かけたりするのはやめましょう。また 私たちは靴を履いていて気がつかない場合が多いですが、アスファルトの温度は日光が当ると大変高温になります。 犬は人間よりも体高が低いので、私たちよりもアスファルトの熱の影響を受けてしまいます。 散歩に出る時に、アスファルトを触ってみるなどして確認してみて下さい。 これから梅雨のシーズンも湿度にも注意していただき、ワンちゃんにとっても人間にとっても快適な夏を迎えましょう。
フィラリアって何?
フィラリアって何?
寒さもひと段落し、春風が気持ちよく感じられるようになってきました。
人間にとっても、動物たちにとっても過ごしやすくなり活動的になれる季節ですね。
暖かくなると‘そろそろフィラリアの予防をしましょう’なんて文句をよく耳にされると思います。しかし、実のところフィラリアって何でしょう?
‘フィラリア’とは犬が蚊に刺されて感染する心臓の寄生虫です。人間も蚊に刺されると感染するのですが、白血球という血液成分が防御してくれるためフィラリアは人間の体の中で成長することはできません。しかし、犬の白血球はなぜかフィラリアを防御する機能がなく感染してしまいます。
蚊から犬の体に感染したフィラリアの子虫は犬の体の中を成長しながら自由に移動して、親虫になる頃心臓にたどり着き、そこを我家に決めて子供を産み始めます。大人になったフィラリアはそうめんほどの太さで長さは15~20cmほどもありますから、心臓がフィラリアの住み家になってしまうと血液の通り道がなくなってしまいます。そして様々な症状から死に至るのです。東海地方では、二夏予防しないと89%、三夏予防しないと92%のワンちゃんがかかってしまうと言われています。
予防の前に
生後4ヶ月以上のワンちゃんはまず血液検査を行います。なぜなら、すでに心臓内にフィラリアの親虫が存在した場合治療が必要となるからです。また親虫が生産した子虫が血液中に循環している場合、知らずに予防薬を与えるとアレルギーやショック症状を起こす可能性があるためです。昨年度予防をしているワンちゃんもきちんと予防できているかを簡易的な血液検査にて行います。また当院ではこれを機会に一緒に健康診断のための血液検査もお勧めしています。
予防の時期
蚊が媒介する病気ですのでフィラリア予防は蚊が活動するシーズンと大きな関係があります。蚊は気温室温が14度以上になると吸血活動を開始し、14度以下では刺すことなく活動停止、または死にます。つまり犬がフィラリアに感染する可能性は蚊が活動している期間と重なります。南北に細長い日本では南の沖縄と北の北海道では蚊の活動時期に何ヶ月ものズレがあります。そのため○月から○月までが蚊の活動期間ですと全国共通でいうことはできず、各々の地域のその年の蚊の発生状況によって○月から○月までが予防シーズンとなるのです。愛知県域での蚊の発生時期は4月下旬から11月中旬といわれています。そのため、5月から12月まで月1回の内服投与を行います。
予防薬について
蚊の活動期間に対して投薬期間が1ヶ月ずつうしろにずれるのは、フィラリア予防薬は実は?予防?ではなく、感染してから対処する?治療?だということを意味しています。つまり、蚊に刺されて子虫が犬の体内に入ってしまってから1ヵ月後に薬が効く虫に発育したものをまとめて駆虫するのです。ですから、蚊が完全にいなくなったと思ってから1ヵ月後に忘れずにシーズン最後の投薬をしてください。
フィラリアはきちんと予防をすれば感染を防げる病気です。予防効果100%の薬があるのにフィラリアにかかってしまうとしたら、それは飼い主さんの責任です。フィラリアにかかった犬は苦しみぬいて最期を迎えます。そうならないために、そうさせないために、ぜひフィラリア予防の知識をみなさん一人一人が広めてください。
犬の鼻が乾いて居たら病気なの?
犬の鼻が乾いて居たら病気なの?
一般的に、犬の鼻が乾いていたら病気だと言われていますが本当にそうなのでしょうか?犬の鼻の先端(被毛の生えていない部分)を鼻鏡(びきょう)といい、通常いつも湿っぽく濡れています。
濡れている理由は、登山家や探検家が微妙な風の向きを知るために、人差し指を舐めて垂直に立て、皮膚感覚で判断するのと同じように、犬は鼻鏡で空気の流れを知り、においで仲間や獲物を感知しているようです。
眠っているときに乾いているのは特別異常ではありません。動き出すと自然に濡れてきて光沢が出てきます。病気で熱が出たり、症状が慢性化して長引いてくると乾いてくることがあります。
しかし、逆に鼻炎やインフルエンザなど鼻水が出てきて鼻が濡れる場合もありますし、大きな症状もなく、全身的にも健康なのに鼻鏡の湿り具合が少ないとか、乾燥してカサカサな犬も存在するようです。
ですから、犬の鼻の乾き具合だけで判断せず、何か変化がみられたら動物病院に相談してみましょう。

空気が乾燥して気温が下がる冬は、鼻やのどの粘膜の働きが弱まり、細菌やウイルスの侵入に対する抵抗性が低くなります。そのため、人も動物も風邪などになりやすいと言えます。
また乾燥はお肌の大敵とよく言われますが、病院には乾燥肌のために皮膚病になった動物も来院します。私たち女性にとってお肌は大変重要ですし、風邪などの予防のためにも加湿器などの設置し、乾燥を防ぎましょう。
まだまだ寒い日が続きます。
皆様体調を崩されないようにお過ごしください。




















